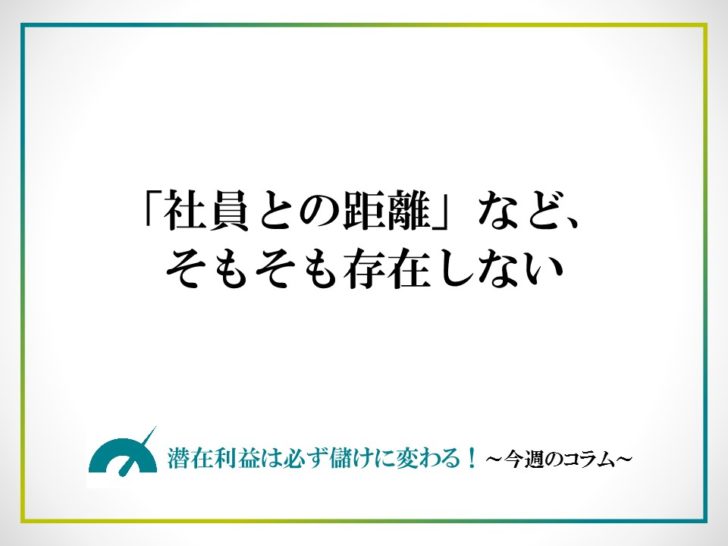
先日参加したある異業種交流会での一コマです。30代前半の若手経営者(A氏)と40代後半のベテラン経営者(B氏)と3人で雑談をしていた時のことです。
B氏がA氏に対して、「君は学生時代の同級生を社員として雇っているよね。昔からの友人というのも分かるけど、仕事の上では立場が全く異なるのだから、付き合い方には一線を画した方がいいと思うよ。」と助言していました。A氏は2代目経営者で高校時代の同級生を縁あって数年前から社員として雇用しており、その集まりにも当人を連れてきていました。
B氏の言うとおり、彼ら二人の会話を聞いていると、そこには経営者と社員という立場の違いは感じられず、いわゆるタメ口というもので、友達同士の会話にどうしても聞こえてしまうのです。B氏がそれとなく助言されたのも、その辺りの様子に先輩経営者として違和感を覚えたからに相違ありません。
同じようなケースは、世の中の中小企業に多く見受けられます。ただ、その状況が問題なのではなく、その状況を経営者としてどう受け取り、自分の立場に照らして、どのように昇華させていくのかが重要なのです。
今まで数多くの経営者にお会いしてきた中で、経営者が友人を役員として、または幹部社員として迎え入れているケースを何件も見てきました。その背景は様々ですが、経営者としてどういった接し方をしていけばいいのか悩まれている方も少なからずおられました。
社員が友人かどうかに関わらず、経営者としてどういった距離感を持つべきか悩まれている方も多いと聞きます(距離感云々に囚われている段階で、そもそも社員を掌握できていない訳ですが)。ここで、社員に対する接し方という切り口で見た場合、「躊躇なく社員に歩み寄るタイプ」もおられますし、逆に「社員から歩み寄ってくるのを待つタイプ」もおられます。
ここで上げたのは両極端ですが、気にすべきは、「自分から歩み寄るタイプは、自らの視点を社員レベルに合わせたまま、元に戻すことを忘れていないか?」、もしくは「社員が歩み寄ってくるのを待つタイプは、自らの視点を社員に近づけるのを忘れていないか?」ということです。
つまり、前者は、経営者が社員に同化し、ただの友達になり、経営者として本来持つべき視点を失くしているケースです。後者は、経営者が社員と交わろうとせず、常に立場の違いによる距離感にこだわり続けているケースです。いずれのケースも、経営者が社員を掌握できるとはいえません。
巷では、社長のコミュニケーション術といったようなノウハウ本も売られていますが、これは経営者と社員との間に距離があることを前提としています。しかし、そもそも、経営者が自己重要感を常に薄めていれば、社員との距離感などという概念は生まれないので、コミュニケーション術などというノウハウが登場する余地などないのです。
自己重要感とは、経営者に限らず人間なら誰しも持つ、自分で自分を大切にしたい本能のようなものなので、それを常に充足させたいという欲求を持つのも自然のことです。ただし、経営者という立場での自己重要感は薄めることが必要です。
と言うのは、もし、経営者としての自己重要感を薄めることができていない場合、「私はこの会社で一番偉い人間だ!」とか「私が一番なんだから社員は私の言う通りにしていればいいんだ!」といった自己主張が頭をもたげてきます。社長が立派かどうかといったことは、社員が感じればいいことであり、経営者が強要するものではありません。
このような経営者は距離感にこだわって、自分から社員に歩み寄ることをしません。
逆に、自己重要感を薄めている経営者は、時間があれば社内を歩き回り、社員に話しかけ、仕事上でもプライベート上でも情報収集を続けます。社長室で執務中でも基本的にドアは開けっ放しにして千客万来の状態を作っています。
なぜか?
そこには、「社員を出来る限り掌握して、社内を一枚岩にすることが、この厳しい環境変化に対応していくためには必要だということが分かっているからです。だから、うるさがれようと何だろうと、そこに躊躇はないのです。
このような経営者の場合、社員との間に距離が生まれるはずもありません。それどころか、そもそも「距離感」という概念がないのです。
経営者としての視点を常に持ちながら、躊躇なく社員に歩み寄り、社員のことを我がことのように共有しようとすることに関して、社員がどう思おうと意に介さない。なぜなら、自己重要感の充足を社員に求めていないので、好かれようと嫌われようと、それに関する良し悪しの尺度を持ち合わせていないからです。
しかも、得てして、このような経営者ほど、すべての社員から愛されてやまない存在になっているのです。
あなたは、経営者としての自己重要感を限りなく透明に近づけた状態で、社員に接していますか?
