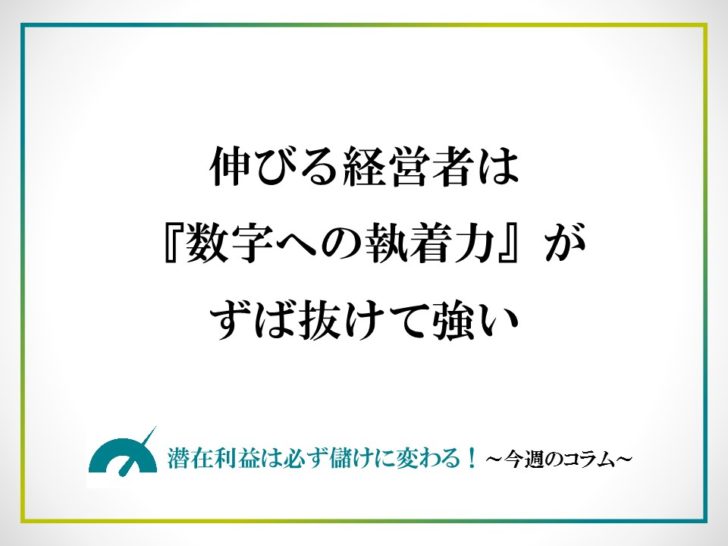
ここ数年来、「経営者は数字に対して強くなければいけない」というフレーズをよく聞きます。
書店に行くと、このフレーズを後押しするかのように「これだけは知っておきたい経営者としての決算書の見方」とか「経営者が押さえておくべき経営指標はこれだけ」などといった類の書籍が所狭しと並んでいます。
経営者と数字を結び付けるこのフレーズは「経営者は元来数字には強くない」であるかのような決め付けから端を発している様にも見えます。
では、経営者が強くなければいけない「数字」とはそもそも一体何を指すのでしょうか?
「数字」という言葉は非常に漠然としているので、「経営者が強くなるべき数字」の意味を明確にすることなく、「経営者たるもの数字に強くなければいけない」といった曖昧模糊とした主張が独り歩きすることは、経営者の数字に対する取り組む方向性を誤らせることにも繋がります。
実は経営者には、「強くならなければいけない数字」と「強くなる必要のない数字」があります。数字という漠然とした言葉の意味を定義付けることで、経営者が向き合うべき数字、すなわち「強くならなければいけない数字」とは何なのか、を明確にしたく、今回のコラムを書きました。
さて、巷に溢れている経営者向けの書籍やセミナーの多くは、「数字イコール会計経理的な数字」という考え方を色濃く出しています。が、果たしてそうでしょうか?
確かに、企業経営の巧拙は、最終的に業績数字で評価されます。そのため、「経営者たるもの会計経理に強くあるべき」との論法で、経営者と会計経理を結び付ける領域に、コンサル関係者や出版業界が「すわ、ビジネスチャンス!」とばかりに、フォーカスを当ててきた経緯があるかも知れません。
今まで私がお会いしてきた数多くの経営者を振り返ってみた場合、会計経理に強くない経営者が大半です。しかし、経営者が会計経理に強くない会社でも、長きに亘り業績を上げている会社はゴマンとあります。ということは、「経営者が強くなければならない数字」とは、会計経理的な数字ではないのです。
会計経理とは、会社が展開している事業の全ての動きを、日本国内で合意を得ている一定の会計税務基準にもとづき、複式簿記の手法で数字で表現していく機能です。その集大成が、年度決算書であり、税務申告書であるのです。
会計経理は、会社の中で果たされるべき機能としては必要不可欠なものですが、一方で専門性が非常に高く、経営者が優先的に注力する領域ではありません。ということは、会計経理の集大成としての年度決算書、税務申告書も、経営者が詳細まで把握する必要性の無いものです。
では、「経営者が強くなければならない数字」が、真に意味しているものは一体何でしょうか?
それは、「会社内の各業務プロセスの中で、どのプロセスをどれだけテコ入れしたら、結果的に受注がどれだけ伸びるのか、最終的に利益がどれだけ伸びるのか」といった「連鎖的な影響」を数字で把握することを意味するのです。
「数字に強くない経営者」は、この連鎖的影響を数字ではなく、少なくとも感覚的に捉えています。一方、「数字に強い経営者」は、この連鎖的影響を、感覚だけでなく数字でも捉えています。
この連鎖的な影響を、経営者は数字もしくは感覚で捉えることができているからこそ、事業を継続できているのです。
例えば、いくつものバルブを取り付けた水道管があり、最下部にある蛇口から出てくる真水を「利益」に例えてみます。この場合、どのバルブをどの程度開けたり閉めたりしたら、最下部の蛇口からどれだけの量の真水が出てくるのか、すなわち、どれだけの利益を獲得できるのか、予め分かった上で途中のバルブを意図的に開け閉めしているイメージです。
数字に強くない経営者は、最後に出てくる真水の量を感覚的に予測します。
数字に強い経営者は、最後の出てくる真水の量を、感覚だけでなく数字でも予測します。
今までは、数字に強くない経営者も、このように業務プロセスの連鎖的影響を感覚で捉えてこれたので、企業として存続してこれた訳です。
しかし、外部環境が予測不能な事態が頻繁に起きることが常態化している現代において、先の連鎖的な影響を感覚だけで把握する経営(つまり、経験と勘による経営)は時として、かじ取りを誤らせ、会社の存続にブレーキを掛ける方向へ牽引してしまうリスクを孕んでいます。
そこに、連鎖的な影響を数字で捉える力が加われば、会社を誤った方向に牽引してしまうリスクを確実に減らせます。
だからこそ、経営者は数字に強くなる必要があるのです。
さて、そうは言っても、数字に強くない経営者が一足飛びに数字に強くなれるのかと言ったら、それは厳しいですし、そこを最優先に目指す必要もありません。
要は、社長がやらなくても、社員が「連鎖的な影響を数字で把握する機能」を果たせれば、それで事足りるのです。要は、会社としてそういった機能を果たせればいいのです。例えば、経理部や経営企画部などの部署が、その専門的な機能を発揮し、連鎖的な影響を経営判断材料として経営者に提供する。これが正に、「仕組みで会社を回す」ということなのです。
一方で、経営者が数字に強い会社の場合、それはそれで良いのですが、将来的展望を考えた場合、両刃の剣が横たわっていることを忘れてはいけません。
つまり、数字に強い経営者の場合、会社の中で連綿と流れる業務において生まれてくる連鎖的影響を、数字で捉えています。この数字による状況把握を経営者自らが独占して、部下にゆだねることをしないと、部下が成長する機会を奪うことになります。
すなわち、今以上に会社が成長しないリスクを孕んできます。そういう意味での両刃の剣なのです。
理想は、数字に強い経営者が、連鎖的影響を数字で抽出する役割を、敢えて部下に権限委譲し、経営者はその結果を受け取る側に回る、という状況です。
最後に一点だけ付け加えます。
冒頭でお伝えしたように、巷に氾濫する経営者向けの書籍やセミナーで盛んに喧伝されている「経営者に求められる数字の力」は、会計経理的な領域や経営指標といったアナリスト的な知識を習得することが必要であるかのような様相を呈しています。
これでは、会計経理的な数字や経営指標的な数字に対する「理解力」や「吸収力」を求めているように捉えられてしまいます。
しかし、それは本質的に誤りです。
経営者が数字に関して備えるべき能力は、「理解力」でも「吸収力」でもありません。備えるべきは、「執着力」なのです。
執着力とは、数字で把握した業務プロセス内の連鎖的な影響のコントロールにどれだけ拘るか、その度合いを指します。最終利益をこれだけ確保するためには、上流にあるどのプロセスをどれだけコントロールして、その結果どれだけ受注を確保し、売上を作っていかなければならないのか、ということにどれだけ執着するかということなのです。
例えば、経営者の数字に対する理解力や吸収力が高くても、執着力が希薄な場合、連鎖的な影響を数字で把握できているだけで、それをコントロールに至らない可能性があります。それでは、企業成長にとって意味がありません。
逆に、理解力や吸収力が希薄であっても、執着力がずば抜けていたらどうでしょうか?
部下に指示を出して経営者自らの執着力を充たすための経営判断材料を、とことん追求させます。その場合、経営者にアナリストのような素養がなくても、数字に対する執着心が起爆剤になって、部下は鍛えられて、会社の成長の礎が作られていくものです。
以上のように、経営者が強くなければいけない数字とは「会社内で連綿と流れている各業務プロセスの連鎖的影響を数字として把握したもの」であり、その数字に対して備えるべき能力は「執着力」です。それが結果的に利益の創造に繋がっていくのです。
あなたは、数字への執着力がずば抜けて強いですか?
